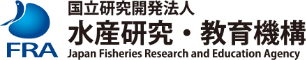宇治川のオイカワ等における腹口類吸虫の寄生事例とその生活環の解明
[要約]
淀川水系宇治川の天ヶ瀬ダム下流域において大量発生したオイカワ等の衰弱魚に関して、その発生原因が腹口類吸虫のメタセルカリアの大量寄生による病気であることを明らかにするとともに、本吸虫のほぼすべての生活環を明らかにすることができた。さらに、ダム下流域での河川流量の多寡がオイカワ等へのセルカリアの寄生数に影響することも明らかにした。
京都府立海洋センター
[連絡先]07722-25-0129
[推進会議]日本海ブロック
[専門]病理
[対象]寄生虫
[分類]行政
[背景・ねらい]
平成12年1~3月に淀川水系宇治川の天ヶ瀬ダム下流域において、オイカワ等の衰弱魚が大量に発生し、マスコミにも奇病として取り上げられ大きな問題となった。この事例における衰弱魚の発生の原因を調べるとともに、原因となった腹口類吸虫の生活環を解明する。
[成果の内容・特徴]
- 寄生虫学的並びに病理組織学的検査により、衰弱の原因は腹口類吸虫のメタセルカリアの大量寄生による 病気であることが明らかとなった(写真1)。
- 我が国の淡水魚における腹口類吸虫の寄生例は今回が初めてである。
- 一般的に腹口類吸虫の生活環は第一中間宿主(貝類)、第二中間宿主(魚類)及び終宿主(魚食性魚類あるいは両生類)を必要とする。今回見つかった吸虫の生活環を調査したところ、第一中間宿主はカワヒバリガイであり(写真2)、第二中間宿主はオイカワ、コウライモロコ等のコイ科魚類で、終宿主はビワコオオナマズであった。
- 宇治川のカワヒバリガイにおけるスポロシスト幼虫の寄生、成熟状況を調べたところ、 寄生率は1.5~6%であり(図1)、10月以降に成熟して、セルカリアを放出させることが判った。しかし、2月には放出盛期は過ぎるようであった。
- 以上のように、本吸虫のほぼすべての生活環を明らかにすることができた。
- さらに、オイカワ等へのセルカリアの寄生数は天ヶ瀬ダム下流域での河川流量が少なくなると増加し、多くなると減少することも明らかになった。
[成果の活用面・留意点]
- 宇治川においては本吸虫の生活環が成立し、すでに定着していると判断された。外来二枚貝類であるカワヒバリガイの未侵入の河川では、今後カワヒバリガイとともに本吸虫が侵入する可能性がある。外来魚介類の侵入により、未知の病気が国内に定着する好例と考えられた。
- オイカワ等へのセルカリアの寄生数は天ヶ瀬ダム下流域での河川流量の多寡によって左右されるところから、上流にある琵琶湖での渇水状況や天ヶ瀬ダムの放水状況 に留意することが重要と考えられた。
[具体的データ]
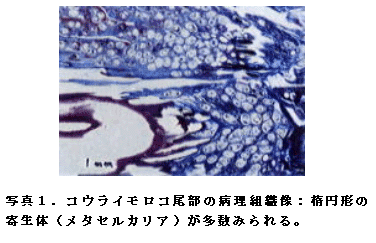
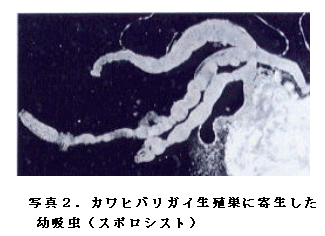
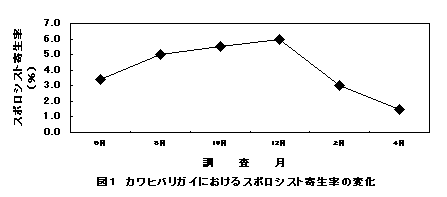
[その他]
研究課題名 :宇治川のオイカワ寄生虫調査(平成11年度:府単費、平成12年度:補助事業)
研究期間 :平成12年度(平成11~12年度)
研究担当者 :中津川俊雄
発表論文等 :なし