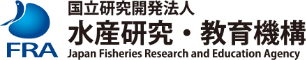アユの種苗由来判別法の開発
福井県内水面総合センター・調査研究G
[連絡先]0776-53-0232
[推進会議]内水面
[専門]資源生態
[研究対象]あゆ
[分類]調査
[ねらい・目的と成果の特徴]
- 河川には遡上あるいは放流により、海産アユ、湖産種苗および人工種苗の3種類が生息している。外部形態の違いからこれらを区別する判別手法を開発する。
- 側線上方横列鱗数と下顎側線孔数を計数することにより、湖産種苗の一部と人工種苗アユを判別することができた。
[成果の活用面等]
- 河川放流したアユの放流効果の把握、あるいは資源量の推定等に応用できるほか、種苗生産において河川で採捕した親魚を用いる場合、由来判別を行い湖産アユを排除し、生産したアユに遺伝的影響のないようにすることに利用できる。
[具体的データ]
人工種苗は13~18枚、海産アユは19~22枚であった。湖産種苗のうち、琵琶湖から周辺河川に遡上した種苗と琵琶湖で採捕後短期間養成した種苗は23~27枚、採捕後長期養成した種苗や湖産親魚を用いた人工種苗では16~26枚であった。このことから、18枚以下は人工種苗、23枚以上は湖産種苗と判別できる。
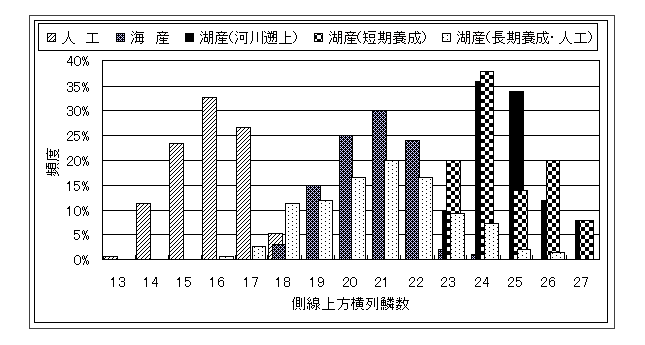
図1 アユ種苗別の側線上方横列鱗数
海産アユおよび琵琶湖から河川遡上した湖産種苗、いわゆる天然魚は側線孔が4個であるが、人工種苗あるいは養成した湖産種苗では側線孔が4個とは限らない。そのため下顎側線孔が左右4個でない個体は、海産種苗や河川遡上した琵琶湖産種苗以外であると考えられた。
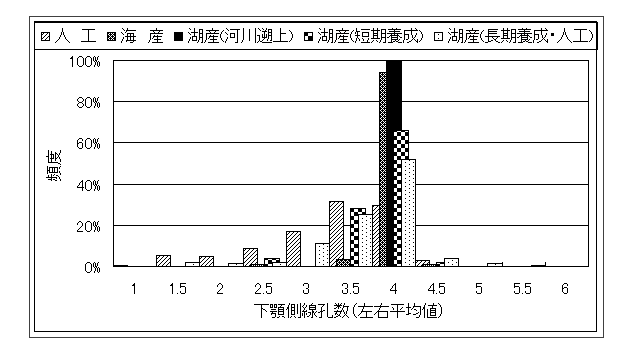
図2 アユ種苗別の下顎側線孔数
側線上方横列鱗数が、18枚以下は海産親魚を用いた人工種苗、23枚以上は湖産種苗(河川遡上、短期養成)と判別でき、19~22枚で下顎側線孔が4個以外は、湖産種苗(長期養成、湖産親魚を用いた人工種苗)と判別できると考えられた。