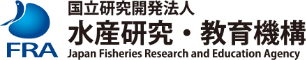2025(R07). 8.13 ジャパン・インターナショナル・シーフードショーに出展します
令和7年8月13日
国立研究開発法人水産研究・教育機構
開発調査センター
深海性の低・未利用魚の活用による漁業と加工業を繋げる取り組みをご紹介します
|
近年、スルメイカやサバ類等の漁獲量減少により、水揚げ金額の減少や加工原料不足が生じています。開発調査センターは、このような問題解決のため、これまで利用されていなかった低・未利用魚に注目し、環境変化に強い地域水産業となるべく様々な取り組みを進めています。
開発調査センターは、令和5年から青森県八戸地区であまり活用されていなかった深海域での操業調査を実施し、漁獲された低・未利用魚の試作加工品開発までを行いました。操業調査の結果、低・未利用魚は最大1日・1隻10トンまで漁獲可能となり、八戸地区の漁業者による水揚げは増加しました。低・未利用魚の水揚げ増加により、八戸地区での加工業者・鮮魚店による総菜等への利用も増加しました。
これらの成果について、第27回「ジャパン・インターナショナル・シーフードショー」でセミナー講演(水産研究・教育機構特別セミナー① 2025年8月21日13時00分~13時35分「深海性の低・未利用魚をもっと身近に」)を行います。原料特性の分析や加工品の試作等の結果についても、共同研究機関である(地独)青森県産業技術センター食品総合研究所の研究者よりご紹介します。
テナガダラのスパイスカレー(下写真)の試食を含めたブース展示(小間番号E-73)も行います。
青森県太平洋海域でソコダラ類(テナガダラ等)やゲンゲ類を中心に調査
用船:青森県八戸機船漁業協同組合所属の第五十五興富丸、第六十二新生丸
期間:令和5年4月1日~5月31日、令和6年3月15日~6月15日、
令和7年3月1日~5月31日




テナガダラとその試作加工品 製品化例:一夜干し 肝共和え
(左:原魚、右:試食提供するスパイスカレー) (有限会社マルコー田中商店提供)
※ 「ジャパン・インターナショナル・シーフードショー」は、商談や情報交換等のビジネスを目的とした事前登録制の展示商談会です。
https://seafoodshow-japan.com/tokyo/
お問い合わせ先
本件照会先:国立研究開発法人 水産研究・教育機構
開発調査センター 櫻井慎大・岡本誠・木宮隆 TEL:045-277-0184(代表)