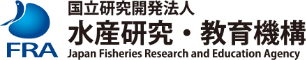2025(R07). 11.11 複雑な潮流でも漁獲可能なまき網とスラリーアイスを活用した長期鮮度保持によって水揚げ金額が増加
令和7年11月11日
国立研究開発法人水産研究・教育機構
複雑な潮流でも漁獲可能なまき網とスラリーアイスを活用した長期鮮度保持によって水揚げ金額が増加
|
概要
九州を拠点とする大型まき網漁業の主な漁場である東シナ海では、近年、海洋環境の変化により夏季に複雑な潮流が多く発生し、操業できない状況が増えています。このような潮流でも操業可能な漁具を開発するとともに、漁獲物の鮮度保持期間を延長して帰港回数を減らすことが、コスト削減の重要な課題となっています。
水産研究・教育機構 開発調査センターは、令和6・7年の夏季に東シナ海で、まき網の一部の網目を最大4.2倍に拡大した改造漁具での操業試験と、スラリーアイスを用いた漁獲物の長期鮮度保持試験を実施しました。
網目を拡大した改造漁具による試験では、従来の漁具より約1.4倍速く沈降したことから、潮流の影響を受けにくいと考えられました。令和7年には、従来の漁具では操業が不可能な潮流下で3回の操業を行い、マアジ、マサバおよびゴマサバを中心に合計約267トンを漁獲し、約3,100万円を水揚げしました。
スラリーアイスで最大4日間保蔵した漁獲物の鮮度が、従来の2日間保蔵の漁獲物と同等であることを科学的に証明し、市場でも十分な評価を得ました。また、スラリーアイスを用いた長期の鮮度保持により、1回の航海で2航海分の運搬に成功しました。
本調査では、改造漁具による操業機会の増加およびスラリーアイスを活用した長期保蔵による漁獲物運搬の効率化により、水揚げ金額の向上を実証しました。西日本では、船団を構成する漁船数を5隻から3~4隻に減らすミニ船団化が普及しつつあり、少ない隻数の船団であっても、水揚げ金額を確保できる更なる効率化が求められています。今後は採算性の評価を行い、あじ類・さば類の安定供給を担うまき網漁業の持続的発展に寄与していきます。
調査結果の詳細は、令和7年度調査結果概要(開発ニュース)をご覧ください。
https://www.fra.go.jp/jamarc/work/gaiyo/r7chousagaiyou.html

改造漁具での操業風景

スラリーアイス魚倉内の漁獲物

水揚げ直後のマアジ
お問い合わせ先
本件照会先:国立研究開発法人 水産研究・教育機構 開発調査センター TEL:045-277-0184(代表)
漁業第一グループ 神村裕之 山﨑恵市 横田耕介