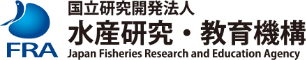2025(R07). 3.26 道東太平洋沖における深海生物資源の分布状況調査を開始します
令和 7 年 3月 26日
国立研究開発法人 水産研究・教育機構
道東太平洋沖における深海生物資源の分布調査を開始します
|
近年の気候変動にともなう海洋環境の変化は我が国の漁業生産に様々な影響を及ぼしています。例えば、スルメイカやサンマといった、漁獲量が多く国民の水産物消費を支えてきた主要魚種の不漁が継続し、また、複数の魚種の分布生態も目に見えて変化しています。これらの現象は、各地域の水産物の供給不安やそれにともなう価格高騰を引き起こし、多くの漁業者の経営基盤を揺るがしています。
このような中、水産業の健全な発展や水産物の安定供給を図ることを目的として、様々な環境変化に柔軟に適応可能な新たな漁業生産体制を構築する必要性が高まっています。その対応策の一つとして、未利用・低利用の漁場や魚種の積極的な活用があります。
当機構開発調査センターは、海洋エンジニアリング株式会社、東京大学生産技術研究所と株式会社ディープ・リッジ・テクで構成される共同企業体への委託研究を通じて、これまでほぼ利用されていない道東太平洋沖の水深800m~2000m程度の深海域の漁場調査を開始します。本調査は、先端技術を駆使した自律型海中ロボット(AUV:Autonomous Underwater Vehicle)を用いた海底付近の映像収集と試験採集を組み合わせて、同海域の深海生物資源の分布生態や現存量に関する情報を取得します。
本調査により商業利用の可能性が見込める資源が確認された場合、この資源の有効活用に向けた漁業生産体制の構築を見据えて、漁具漁法等に関する技術開発試験や実証操業結果に基づく収益性評価を行うことを想定しています。
【調査期間(ただし、天候やその他の理由により変更の場合あり)】
1期:令和7年4月1日(火曜日)~令和7年5月1日(木曜日)
2期:令和7年6月1日(日曜日)~令和7年7月9日(水曜日)
3期:令和8年1月20日(火曜日)~令和8年2月18日(水曜日)
【調査船】
第一開洋丸(総トン数:1406トン):AUVによる探査、海底地形情報の収集を主に担当
第六開洋丸(総トン数:443トン):試験採集を主に担当
関連情報
東京大学 生産技術研究所
AUV による道東太平洋沖における深海生物資源の分布状況を把握する調査を開始します
(2025.3.26)
URL:https://www.iis.u-tokyo.ac.jp/ja/news/4723/
お問い合わせ先
国立研究開発法人 水産研究・教育機構 開発調査センター TEL:045-277-0184(代表)
(担当者) 実証化企画室 室長 貞安一廣
漁業第三グループ リーダー 加藤慶樹