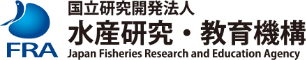広島県沿岸域の海洋環境の推移
広島県水産試験場 資源環境部
[連絡先]0823-51-2171
[推進会議]瀬戸内海ブロック
[専門]海洋構造
[研究対象]海洋変動
[分類]調査
[ねらい・目的と成果の特徴]
- 広島県沿岸域における30年間に及ぶ海洋環境モニタリングデータから海洋環境の変化を検討する。
- (1)瀬戸内海区水産研究所と協力して、1972年から2001年までの30年間の調査結果を解析した。
- (2)表面海水温は上昇傾向にあり、特に秋季から冬季の水温上昇が顕著であった。
- (3)栄養塩類については窒素源のうちアンモニア態窒素の減少が顕著であったが、リン源については目立った変化は見られなかった。
[成果の活用面等]
- 本成果は漁海況予報のほかに、富栄養化や地球温暖化などによる漁場環境への影響評価のための基礎データとして活用できる。
[具体的データ]
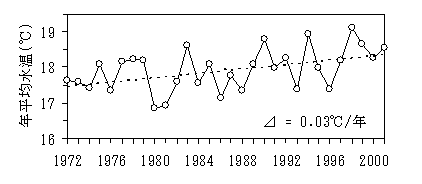
図1.広島県沿岸域における表層水温の経年変化.
表層水温の推移を直線で近似すると傾きが0.03となり,表層水温が1年あたり0.03℃の割合で上昇していることが分かった。これによると広島県海域では過去30年間で約1℃水温の上昇があったこととなる。
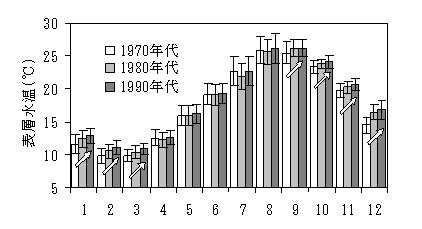
図2.広島県沿岸域における表層水温の年代別季節変化.
値は平均値と標準偏差を示す。矢印は月別に年代毎の表層水温を一元配置分散分析によって解析した結果、pが0.05以下となったことを示す。すなわち、年代間で表層水温に有意な差があることを示しており、過去30年間で秋季から冬季にかけて、水温上昇が顕著であったことを表している。
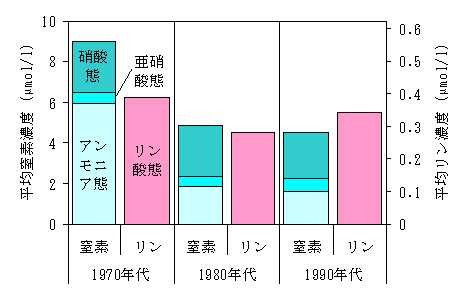
図3.広島県沿岸域における栄養塩の年代別変化.
無機態窒素は1970年代には平均で約9μmol/lであったが、1980年代及び1990年代には5μmol/l以下まで低下した。無機態窒素の減少の主な要因はアンモニア態窒素の減少によるもので、1970年代には無機態窒素の66%を占めていたが、1980年代以降は37%以下にまで低下している。リン酸態リンについては1980年代にやや低下したが、無機態窒素の減少に比べると低下率は小さく、過去30年間に大きな変化はみられなかった。