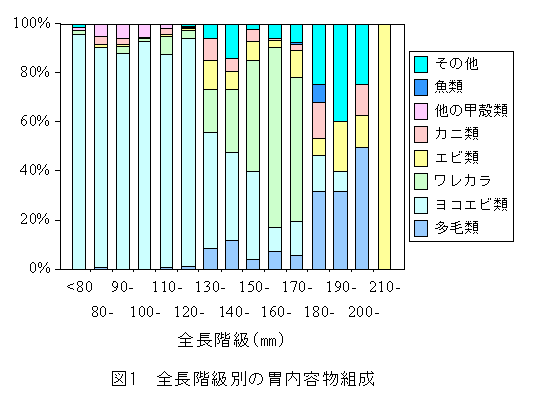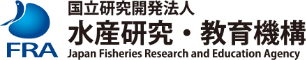マアナゴの稚魚は何を食べて大きくなるのか?
兵庫県立農林水産技術総合センター 水産技術センター 資源部
[連絡先]078-941-8601
[推進会議]瀬戸内海ブロック
[専門]資源生態
[研究対象]他の底魚
[分類]研究
[ねらい・目的と成果の特徴]
- 兵庫県瀬戸内海域のマアナゴの漁獲量は、1993年頃まで1500~2000トン/年で安定していたが、1994年以降急激に減少し、1999年には562トン/年まで落ち込んだ。2000年には772トン/年とやや回復したものの、マアナゴのこのような減少傾向は主要魚種の中でも際立っている。
- マアナゴ漁獲量の変動要因を明らかにし、対策をとるためには、「各成長段階ごとに住んでいる場所」や「何を食べているのか」等の生物・生態情報を詳しく知る必要がある。
- 底生生活へ移行した直後から漁獲される大きさになる直前まで、マアナゴが何を食べて成長するのかを初めて明らかにした(図1を参照のこと)。
- マアナゴ幼稚魚の生息域や生息環境を推定することが出来るようになった。
[成果の活用面等]
- マアナゴの資源を増大させるためには、漁具の改良による幼稚魚の保護、漁期・漁場の制限、増殖場の造成などの方法が考えられる。今後、本成果はマアナゴの幼稚魚を保護していくための重要な資料となる。
[具体的データ]
餌生物の個体数から見た、マアナゴの全長階級ごとの胃内容物組成(%)を図1に示した。
着底直後のマアナゴは、主に甲殻類を食べて成長し、大きくなるとともに、多毛類の出現頻度が高くなってくることがわかった。また食べている甲殻類の種類も、成長とともに大きく変化する様子がうかがえる。
全長階級120mm以下のマアナゴが食べている甲殻類は、ほとんどが小型のヨコエビ類である。130mm以上になるとヨコエビに代わって、ワレカラ、中型のエビ・カニ類を食べるようになるが、多毛類も徐々に増えてくる。180mmを越えると大型のエビ・カニ類ならびに多毛類の出現頻度が高くなってくる。
このように、マアナゴは大きくなるにつれて、餌生物のサイズが大きくなるとともに(大型化)、その種類数も増加する(多様化)傾向が見られ、周りの餌料環境に制約を受けにくい効率的な食事へと変化して行く様子がうかがえる。