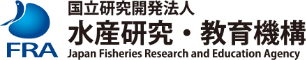チョウセンハマグリ資源に及ぼす遊漁者の間引き圧力について
[要約]
2mmサイズ人工種苗の汀線域放流によって生き残ったチョウセンハマグリ稚貝が殻長15mm以上に成長した段階で、遊漁者の潮干狩りによってその大部分が間引かれていることから、遊漁者の間引き圧力を推定した。
茨城県水産試験場・浅海増殖部
[連絡先]029-265-7452
[推進会議]東北ブロック水産業関係研究試験推進会議
[専門]増養殖技術
[対象]ハマグリ
[分類]調査
[背景・ねらい]
2mmサイズのハマグリ(チョウセンハマグリ)人工種苗を半閉鎖的水域の汀線域へ放流(平成10年3ヶ所、平成11年3ヶ所へ放流)したところ、放流から約1年後の生残率が6~56%であった。しかし、殻長15mm以降になると生残率が急激に低下し、放流から約2年後には生残率が0~5%にまで低下してしまうことが明らかとなった。
殻長15mm以降の急激な生残率の低下原因の一つとして、遊漁者の潮干狩による間引きが考えられたので、実際に遊漁者が潮干狩りによって間引く数量を定量的に明らかにするための調査を実施した。
[成果の内容・特徴]
- 平成10年及び平成11年放流群(鹿嶋市平井海岸)の生残率及び平均殻長の推移を図1、2に示した。
- 平成10年、11年放流群とも殻長15mm以降に生残率が急激に低下し、放流から2年後に生残率が平成10年放流群は2%、11年放流群は1%まで低下した。
- 人工種苗の生残が良好な鹿嶋市平井海岸(突堤などの人工構築物に囲まれた約1kmの汀線域)において平成12年4~5月、平成13年4~5月の2回、それぞれ連休を夾んで2週間の間隔を開けて遊漁者による間引き数量を推定した。
- その結果、平成12年の調査では現存量(3月13日現在62万個)の27%、平成13年の調査では現存量(3月28日現在23万個)の32%がそれぞれ間引かれていることが明らかとなった(表1)。なお、その間の推定遊漁者数(聞き取りから推定)は、平成12年、平成13年ともに延べ300人前後と推定された。
- サイズ別の減少率をみると、平成12年の調査では殻長20mm以上、平成13年の調査では殻長15mm以上の稚貝が選択的に間引かれ、殻長15mm以下の稚貝はほとんど間引かれていないことが明らかとなった。なお、水試職員が実験的に徒手採捕を行ったところ、1m2当たり100個以上の密度でハマグリ稚貝が分布している場合、1時間当たり500個程度採捕できることが明らかとなった。
[成果の活用面・留意点]
- ハマグリは殻長30mm前後になると自ら粘液紐を出して沖合へ移動すると考えられているが、殻長15mm以上になると遊漁者に大量に間引かれることが明らかとなったことから、遊漁者に間引かれる前に、沖合へ移植することが可能かどうか、移植に適したサイズ・時期・場所及び汀線域での効率的な回収方法・回収コストなどについて早急に検討する必要がある。また、遊漁者に実態をPRして、はまぐり資源の維持管理に理解を促す方策を立てるために活用する。
[具体的データ]
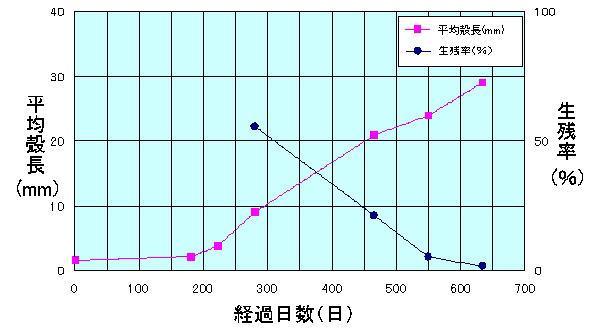
図1 平成10年放流人工種苗の生残率及び平均殻長の推移
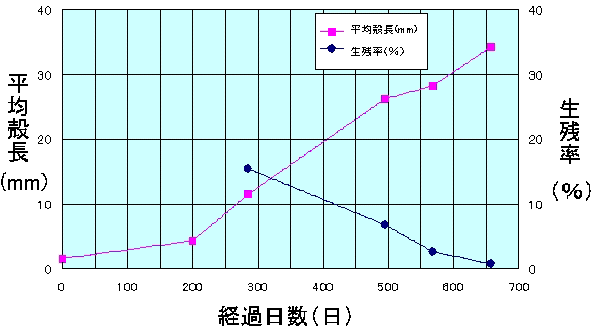
図2 平成11年放流人工種苗の生残率及び平均殻長の推移
| 殻長範囲 (mm) |
採捕個体数(個) | 減少率 (%) |
採捕個体数(個) | 減少率 (%) |
||
| 2000.4.25 | 2000.5.9 | 2001.4.26 | 2001.5.10 | |||
| 10.0-14.9 | 10 | 12 | 120 | 2 | 4 | 200 |
| 15.0-19.9 | 27 | 28 | 104 | 14 | 7 | 50 |
| 20.0-24.9 | 63 | 39 | 62 | 24 | 19 | 79 |
| 25.0-29.9 | 33 | 15 | 45 | 33 | 21 | 64 |
| 30.0-34.9 | 7 | 8 | 114 | 29 | 15 | 52 |
| 35.0-39.9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 150 |
| 合計 | 140 | 102 | 73 | 106 | 72 | 68 |
| 推定生息数 | 23,500 | 17,100 | - | 37,630 | 25,560 | - |
| 調査面積 | 6,000 | 7,000 | ||||
kiren@myg.affrc.go.jp
表1 遊漁者間引き量調査におけるハマグリ稚貝の採捕数
[その他]
研究課題名:二枚貝増殖技術開発研究
予算区分 :県単試験研究費
研究期間 :平成12~13年度
研究担当者:小曽戸誠、山口安男