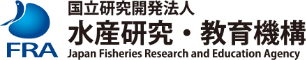有明海における主要珪藻類の休眠期細胞の分布特性
[要約]
有明海の海底泥中における主要珪藻類休眠期細胞(タネ)の存在密度を調べた結果,有明海は珪藻赤潮が発生しやすい海域であること,さらにノリ色落ちの直接的な原因とされたリゾソレニアが休眠期細胞を作らない種であり,その由来が外洋域である可能性があることを明らかにした。
瀬戸内海区水産研究所 赤潮環境部 赤潮生物研究室
[連絡先]0829-55-0666
[推進会議]漁場環境保全
[専門]赤潮・貝毒
[対象]植物プランクトン
[分類]研究
[背景・ねらい]
有明海は養殖ノリの生産漁場として重要な海域であるが,近年同海域では植物プランクトンの大量増殖による赤潮発生が原因で栄養塩が枯渇し,ノリの色落ち現象が頻発している。とくに,平成12年12月から発生した有害珪藻リゾソレニアによる赤潮は,当該海域のノリ養殖に壊滅的な被害をもたらした。そのため,赤潮によるノリ色落ち現象の原因究明は,有明海における安定的なノリ生産をはかる上で緊急の課題となっている。本研究では,有害珪藻赤潮の発生機構を解明するため,有明海海底泥中における休眠期細胞の分布特性を解明することを目的とした。
[成果の内容・特徴]
- 平成13年7月に有明海の24定点において瀬戸内海区水産研究所漁業調査船「しらふじ丸」による採泥調査を実施した。
- 得られた海底泥試料について,終点希釈法により主要な珪藻類(Skeletonema costatum, Chaetoceros spp., Thalassiosira spp.など)の休眠期細胞の存在密度を調べた。
- 珪藻類休眠期細胞の分布密度(上記3群の合計)は,海底泥1立方センチメートル中に4,800細胞から3,195,000細胞(平均730,000細胞)の範囲にあり,ほとんどすべての定点で10万細胞を越えていた(図1)。
- 有明海ではThalassiosira spp.の休眠期細胞が優占することが明らかとなった(図2)。
- 有明海における休眠期細胞,とくにS. costatumと Thalassiosira spp.の存在密度は瀬戸内海における平均値の10倍に上る高い値を示すことが判明した。
- 珪藻赤潮の原因種とされたRhizosolenia imbricataの休眠期細胞は検出されなかった。
[成果の活用面・留意点]
以上の結果から,有明海は珪藻赤潮が発生しやすい海域であること,さらにノリ色落ちの直接的な原因とされたR. imbricataがタネである休眠期細胞を作らない種であり,その由来が外洋域である可能性があることなど,有明海における珪藻赤潮の発生機構を考える上で重要な知見が得られた。これらの成果は,行政対応特研の他課題などと連携することにより,有明海におけるノリ不作問題への対策に資することが期待される。
[具体的データ]
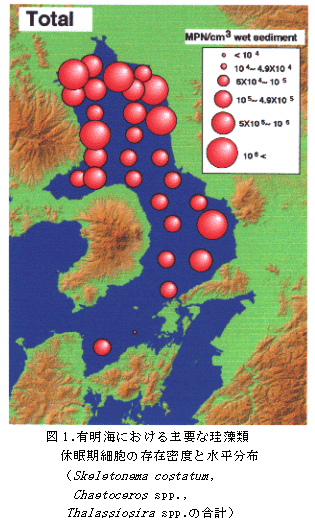
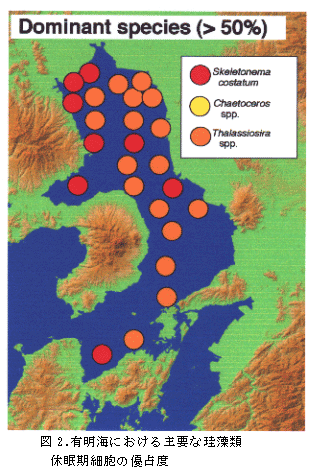
[その他]
研究課題名(委託プロ研):有明海における有害赤潮の生活史と増殖特性の解明(農林水産技術会議)
研究期間:13年度~15年度
研究担当者:山口峰生・板倉 茂
発表論文等:
- 平成13年12月,海洋気象学会・水産海洋学会・日本海洋学会西南支部・長崎大学水産学部,九州沖縄地区合同シンポジウム「有明海の海洋環境」において口頭発表。
- 平成14年4月,日本水産学会春季大会(近畿大学)で口頭発表の予定。