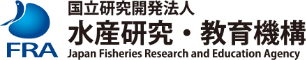UJNR水産増養殖専門部会の歴史
UJNR水産増殖専門部会の歴史概略
設置の経緯
天然資源の開発利用に関する日米会議,通称UJNR (USA-JAPAN Cooperative Program in Natural Resources) は,1964年の第3回日米貿易経済合同委員会において,天然資源の分野で情報,研究資料,専門家及び研究施設を交換することが日米両国にとって極めて有益であるとの合意に基づき,設置された。
水産増養殖専門部会は,UJNRの発足当初から米国側より提案され強い関心の寄せられた分野であり,1967年の佐藤首相とジョンソン大統領の間で日米両国が海洋資源利用に必要な科学技術協力を行う道を求めるとの合意に基づき,1968年10月の第4回UJNR本会議において設立されることが承認されたUJNR専門部会の一つである。
協力の形態
UJNR水産増養殖専門部会は国内においては運営委員会で方針を検討し,日米両国間では合同会議,科学シンポジウム,現地検討会を開催し,情報交換,文献交換,研究者交流,研究成果の紹介と印刷,協力研究等を行っている。本部会は特に研究者の交流や科学シンポジウム及び現地検討会を重視している。現地検討会はその年の合同会議テーマに沿って行われ,これらの活動を通じてそれぞれ相手国の水産増養殖の現状を正しく認識することに努めている。
活動状況
両国間の合同会議等は1974年の第3回日米合同会議以降,毎年,日米交互に開催し現在に至っている。
特に1977年以降,科学シンポジウムの主題を前もって5カ年間,2006年以降は3カ年間にわたり設定し,研究交流を計画的に進めることとしている。
科学シンポジウムで発表された論文は,日米合同会議のプロシーディングとして米国開催時には海洋気象庁(NOAA)のテクニカルレポートとして,また日本国開催時には水産総合研究センター研究報告(2000年までは養殖研究所研究報告)として刊行され,日米双方の関係者を中心に配布されている。
天然資源の開発利用に関する日米会議(UJNR)専門部会
海洋関係専門部会
- 水産増養殖専門部会
- 潜水専門部会
- 潜水船調査技術専門部会
- 海洋構造物専門部会
- 海洋地質専門部会
- 海底鉱物資源専門部会
- 海底調査専門部会
- 太平洋総合観測研究イニシアティブ専門部会
- 沿岸環境科学技術専門部会
非海洋関係専門部会
- 飼料作物改良部会
- 森林専門部会
- 家畜家禽疾病専門部会
- 食品・農業部会
- 有毒微生物専門部会
保全・レクリエーション・公園専門部会 - 地震調査専門部会
防火専門部会 - 耐風・耐震構造専門部会
会議の開催記録
| 回 | 開催月日 | 開催地 | 日米部会長名 | 会議の概要 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1971年 (S46) 10月18日,19日,29日 |
東京・霞ヶ関ビル | 古川 厚 William N. Shaw |
日米共同声明文(1971年和文) ・日米の水産増養殖の現状に関する総括的報告 17課題(日本5課題) ・研究者交流と文献交換に関する基本計画協議 ・日米が抱える問題点の討議 (水質問題,生産の機械化,病気,寄生虫,食害,増養殖適種開発,人工飼料等) ・文献交換 米国から日本 9編 ・現地視察旅行 10月20日-28日 |
||||||||||||||||||
| 2 | 1972年 (S47) 10月16日,27日 |
Washington D.C.(10月16日) Seattle, Washington(10月27日) |
古川 厚 William N. Shaw |
・日米の水産増養殖の現状に関する総括的報告 ・研究者交流と文献交換の計画を具体化 ・第1回研究者交換開始 ・水産増養殖の当面する現状と問題点に関する討議 (共通問題:水産生物の病理と栄養) ・現地視察旅行 10月17日-26日 |
||||||||||||||||||
| 3 | 1974年 (S49) 10月15日,16日 |
東京・霞ヶ関ビル | 古川 厚 William N. Shaw |
・シンポジウム「魚病」 ・研究者交流(日本1名,米国1名)・情報交換・協同研究課題・議事録印刷等の討議 ・研究者交流計画 ・米国側 文献の翻訳システム化,情報のコンピューター化) ・共同研究課題採択「貝類の病気」 ・現地視察旅行 10月17日-26日 |
||||||||||||||||||
| 4 | 1975年 (S50) 10月16日 |
Lewes, Delaware | 古川 厚 William N. Shaw |
・栄養と飼料に関する国際学会と共催 ・共同研究(貝類の疾病 担当:小金沢昭光,Carl Sinderman) ・アルテミア卵の不足と孵化率低下問題に関する協議 ・研究者交流 |
||||||||||||||||||
| 5 | 1976年 (S51) 6月3日 |
京都 | 佐藤重勝 William N. Shaw |
・日本側部会長による過去5ヶ年の活動評価と次期5ヶ年の展望 (佐藤部会長:最近5ヶ年の日本における水産増養殖の進歩を評価する報告書を提出) ・米国部会長による部会活動の目的に関する総括 (水産増養殖に関する情報交換,研究者交流,共同研究計画の推進,国際的情報交換の発展,水産生物生産の増大) ・米国海洋開発計画,水産業振興計画による水産増養殖事業の紹介 ・研究者交流 |
||||||||||||||||||
| 第1次5ヶ年計画(1977~1981年) | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 1977年 (S52) 8月27日 |
Santa Barbara, California | 佐藤重勝 (藤谷 超:会長欠席のため代理出席) William N. Shaw |
・シンポジウム「海藻類の増養殖(国際海藻学会と共催)」 報告 日本3編,米国2編 ・米国における水産増養殖振興法制定計画の紹介 ・両国における藻類生産の現状に関する報告 ・5ヶ年計画立案の提案(日本側:年度毎に主題を決定)
1.放流効果判定法 2.海産魚類養殖 3.サケ類生産における海洋の許容生産力 ・共同研究:貝類の疾病 Sinderman博士による報告 ・研究者交流 ・現地検討会 米国西海岸・南アラスカ水産増養殖施設(アワビ・カニ関連) |
||||||||||||||||||
| 7 | 1978年 (S53) 10月3日,4日 |
東京 | 佐藤重勝 William N. Shaw |
・シンポジウム「海産魚類増養殖」
・現地検討会 四国(ハマチ,マグロ生簀養殖場) |
||||||||||||||||||
| 8 | 1979年 (S54) 10月17日,18日 |
Bellingham, Washington |
佐藤重勝 William N. Shaw |
・シンポジウム「淡水魚類の養殖」報告5題
・現地検討会 キャットフィッシュ・ベイトフィッシュの養殖(アメリカ南部),サケ・スチールヘッド・淡水マス孵化場(北西部) |
||||||||||||||||||
| 9 | 1980年 (S55) 5月26日,27日 |
京都, 国立京都国際会議場 | 須田 明 William N. Shaw |
・シンポジウム「甲殻類の水産増養殖」研究報告3題
|
||||||||||||||||||
| 10 | 1981年 (S56) 10月27日 |
Lewes, Delaware | 花村宣彦 Conrad Mahnken |
・シンポジウム「貝類の増養殖」
・第2次5ヶ年計画確認
Delaware大学海洋科学センター・内務省リータウン魚病研究センター・水産局オックスフォード研究所・メリーランド大学ホーンポイント研究所・水産局ミルフォード研究所・ワシントン州立大学・ピューゲット海峡の養殖場 |
||||||||||||||||||
| 第2次5ヶ年計画(1982~1986年) | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 1982年 |
東京 | 花村宣彦 Conrad Mahnken |
・シンポジウム「サケ・マス増養殖の強化」
・第2次5ヶ年計画の変更
北海道大学水産学部・北海道立水産孵化場森支場・北海道さけ・ます孵化場・北海道さけ・ます孵化場千歳支場・宮城県内水面水産試験場・宮城県栽培漁業センター・石巻ぎんざけ・わかめ・かき養殖場・東北区水産研究所 |
||||||||||||||||||
| 12 | 1983年 (S58) 10月25日 |
Baton Rouge, Louisiana |
多々良薫 (能勢健嗣) Conrad Mahnken |
・シンポジウム「養殖種における繁殖成熟および種苗生産」
|
||||||||||||||||||
| 13 | 1984年 (S59) 10月24日,25日 |
伊勢 | 多々良薫 Conrad Mahnken |
・シンポジウム「水産増養殖における環境問題」
養殖研究所・的矢養蠣研究所・奈良・愛知栽培漁業センター・近畿大学臨海実験所・海洋生物環境研究所・水産工学研究所 |
||||||||||||||||||
| 14 | 1985年 (S60) 10月16日,17日 |
マサチューセッツ州ウッズホール海洋研究所 Woods Hole, Massachusetts |
佐藤重勝 Conrad Mahnken |
・シンポジウム「水産増養殖における最新技術」
・第3次5ヶ年計画確認
ニューイングランド地方を中心に大学・研究所・ふ化場・漁場・民間会社等19ヶ所 |
||||||||||||||||||
| 15 | 1986年 (S61) 10月22日,23日 |
京都 | 池田郁夫 Conrad Mahnken |
・シンポジウム「沿岸域における水産増養殖の強化」
第3次5ヶ年計画を確認 ・現地検討会 10月24日-28日大分県水産試験場・福岡県内水面水産試験場・佐賀県有明水産試験場・西海区水産研究所 |
||||||||||||||||||
| 第3次5ヶ年計画(1987~1991年) | ||||||||||||||||||||||
| 16 | 1987年 (S62) 10月20日,21日 |
Charleston, Soutd Carolina |
能勢健嗣 Conrad Mahnken |
・シンポジウム「水産増養殖における遺伝・育種学研究」
・現地検討会 10月22日-31日 フロリダ・テキサス |
||||||||||||||||||
| 17 | 1988年 (S63) 10月16日-18日 |
三重県伊勢市 | 菅野 尚 Conrad Mahnken |
・シンポジウム「マリ-ンランチング」
・釧路市にてサテライトシンポジウム開催 ・現地検討会 10月19日-23日 北海道東部・オホーツク海沿岸及び東北地方三陸海岸 |
||||||||||||||||||
| 18 | 1989年 (H1) 9月18日,19日 |
Port Ludlow, Washington |
菅野 尚 Conrad Mahnken |
・シンポジウム「水産増養殖における繁殖生理」 ・研究者交流(日本から12名,米国から1名) ・文献交換(日本から94編+1988年度漁業白書英語版,米国から125編) ・共同研究 海産養殖種の病気索引の作製 (ヨーロッパを含めた共同作業要領作製に着手) ・その他(遠洋水研を正式メンバーとすることが了承された) ・現地検討会 9月20日-26日 |
||||||||||||||||||
| 19 | 1990年 (H2) 10月29日,30日 |
伊勢市 | 坂口清次 Conrad Mahnken |
・シンポジウム「魚類の疾病」 ・研究者交流(日本から7名,米国から4名) ・文献交換(日本から130編+1989年度漁業白書英語版,米国から132編) ・共同研究 海産養殖種の病気索引の作製(中止を決定) ・第4次5ヶ年計画案討議 ・次年度シンポジウムテーマの変更を決定 (「集約的・粗放的増養殖」から「栄養」へ変更) ・現地検討会 10月31日-11月7日 |
||||||||||||||||||
| 20 | 1991年 (H3) 10月28日,29日 |
Newport, Oregon | 高木健治 James P. McVey |
・シンポジウム「魚類の栄養」 ・研究者交流(日本から6名) ・文献交換(日本から113編+1990年度漁業白書英語版,米国から51編) ・第4次5ヶ年計画
|
||||||||||||||||||
| 第4次5ヶ年計画(1992~1996年) | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 1992年 (H4) 11月26日,27日 |
京都 | 高木健治 James P. McVey |
・シンポジウム「水産増養殖における環境管理」研究発表22編 ・研究者交流(日本から10名,米国から3名) ・文献交換(日本から124編+1991年度漁業白書英語版,米国から89編) ・共同研究 ・茨城県(水産工学研究所)にてサテライトシンポジウム開催 研究発表4編 ・現地検討会 11月28日-12月3日 茨城・千葉 |
||||||||||||||||||
| 22 | 1993年 (H5) 8月21日,22日 |
Homer, Alaska | 田中邦三 James P. McVey |
・シンポジウム「環境中における養殖種と天然種の相互作用」研究発表12編 ・研究者交流(日本から3名) ・文献交換(日本から65編,米国から163編) ・共同研究 ・現地検討会 8月23日-27日 アラスカ大学海洋・研究センター,牡蠣養殖漁場,サケ孵化場 |
||||||||||||||||||
| 23 | 1994年 (H6) 11月17日,18日 |
三重県伊勢市 | 田中邦三 James P. McVey |
・シンポジウム「サケ・マス類の増養殖とその生物学的統御」研究発表15編 ・研究者交流(日本から2名,米国から1名) ・文献交換(日本から135編,米国から131編) ・新潟市にてサテライトシンポジウム「魚類の増養殖技術」開催 研究発表7編 ・現地検討会 11月19日-26日 富山県水産試験場,新潟県栽培漁業センター,養殖研究所日光支所,国際農林水産業研究センター |
||||||||||||||||||
| 24 | 1995年 (H7) 10月9日,10日 |
Corpus Christi, Texas | 畔田正格 James P. McVey |
・シンポジウム「水産増養殖と水質・環境-魚類およびエビ養殖における排水と水質-」研究発表27編 ・研究者交流(日本から26名,米国から2名) ・文献交換(日本から120編,米国から79編) ・共同研究 1.日本側より科技庁への国際ワークショップ企画の提案紹介 (米国側援助を確約) ・第5次5ヶ年計画に関する討議(両国の背景紹介) ・現地検討会 10月11日-15 テキサス大学海洋生物医学研究所,テキサス農科大学農学実験施設,エビ養殖場,NOAA海洋漁業センター |
||||||||||||||||||
| 25 | 1996年 (H8) 10月16日,17日 |
神奈川県横浜市 | 畔田正格 James P. McVey |
・シンポジウム「水産増養殖と生物の多様性-持続的発展を目指して-」
・第5次5ヶ年計画
|
||||||||||||||||||
| 第5次5ヶ年計画(1997~2001年) | ||||||||||||||||||||||
| 26 | 1997年 (H9) 9月16日-18日 |
Durham, New Hampshire |
上北征男 James P. McVey |
・シンポジウム「魚介類の栄養代謝と増養殖の技術開発」 ・研究者交流(日本から16名,米国から6名) ・文献交換(日本から96編,米国から68編) ・共同研究 1.ヒラメ共同研究(経過報告) ・現地検討会 9月19日-25日 |
||||||||||||||||||
| 27 | 1998年 (H10) 11月11日,12日 |
伊勢 | 加藤 守 James P. McVey |
・シンポジウム「魚介類育種の目標と戦略」
・共同研究
・現地検討会 11月13日-22日 |
||||||||||||||||||
| 28 | 1999年 (H11) 11月6日-15日 |
Oahu, Hawai | 加藤 守 (福所邦彦) James P. McVey |
・シンポジウム「水産増養殖生物の成熟と産卵」
・UJNRサマープログラム(開始を検討) ・第6次5ヶ年計画に関する討議(両国ワーキングチームの提案)・現地検討会 11月8日-15日 |
||||||||||||||||||
| 29 | 2000年 (H12) 11月7日-15日 |
伊勢 石垣 |
中村保昭 James P. McVey |
・シンポジウム「病原生物と防疫」
・第6次5ヶ年計画に関する討議(独法化等により3-5年次の計画確定は避けることで合意) ・石垣におけるサテライトシンポジウム・日米代表打合せ(追加:重要事項のフォローアップについて確認) ・現地検討会 11月9日-15日 |
||||||||||||||||||
| 30 | 2001年 (H13) 12月1日-8日 |
Sarasota, Florida | 中村保昭 James P. McVey |
・シンポジウム「増養殖対象生物の生態と資源増殖」
・UJNR検討委員会分科会(情報化,成果,将来)の設置に合意 ・フロリダ大におけるサテライトシンポジウム・日米代表打合せ(追加:重要事項のフォローアップについて確認) ・現地検討会 12月5日-7日 Trip Report |
||||||||||||||||||
| 第6次5ヶ年計画(2002~2006年) | ||||||||||||||||||||||
| 31 | 2002年 (H14) 10月16日,17日 |
横浜 塩釜 |
松里俊彦 James P. McVey |
・シンポジウム「藻類及び濾過食動物の増養殖」 ・研究者交流 ・文献交換(日本から18編,米国から40編) ・共同研究 ・サテライトシンポジウム-塩釜 ・現地検討会 10月18日-25日 |
||||||||||||||||||
| 32 | 2003年 (H15) 11月17日,18日 |
Davis & Santa Barbara, California | 酒井保次 James P. McVey |
・シンポジウム「甲殻(魚介)類の増養殖と病原生物学」 ・研究者交流 ・文献交換(日本から119編+51編,米国から24編) ・第6次5カ年計画のフォロー ・現地検討会 11月19日-22日 Trip Report |
||||||||||||||||||
| 33 | 2004年 (H16) 11月2日-7日 |
長崎,熊本,鹿児島,福岡 | 酒井保次 James P. McVey |
・シンポジウム「増養殖漁場の生態系および環境収容力」 ・研究者交流 ・文献交換(日本から79+150編,米国から43編) ・第6次5カ年計画のフォロー ・2005年度NOAAワークショップの開催 ・現地検討会 11月4日-5日 |
||||||||||||||||||
| 34 | 2005年 (H17) 11月6日 |
San Diego, California | 酒井保次, Rovert Iwamoto |
・シンポジウム「生態系管理における養殖の役割」 ・研究者交流 ・文献交換(日本から201編,米国から41編) ・5カ年間計画を3カ年計画に短縮 ・現地検討会 11月9日-11日 |
||||||||||||||||||
| 35 | 2006年 (H18) 11月13日-17日 |
三重,和歌山 | 酒井保次, Rovert Iwamoto |
・シンポジウム「増養殖と漁場管理を通じた持続的な水産業の構築」 ・研究者交流 ・文献交換(日本から169編,米国から57編) ・第7次3ヵ年計画のフォローについて ・現地検討会 三重・和歌山 |
||||||||||||||||||
| 第7次3ヶ年計画 | ||||||||||||||||||||||
| 36 | 2007年 (H19) 10月29日,30日 |
University of New Hampshire, Cape Cod (Massachusetts), Milford (Connecticut) | 中野広 Rovert Iwamoto |
・シンポジウム「無脊椎動物の養殖技術」 ・研究者交流 ・文献交換(日本から123編,米国から45編) ・文献交換の見直し ・UJNRの成果の歴史を編纂の検討 ・現地検討会 10月31日-11月2日 |
||||||||||||||||||
| 37 | 2008年 (H20) 10月27日-29日 |
横浜 | 中野広 Rovert Iwamoto |
・シンポジウム「養殖飼料の未来」 ・趣旨:水産養殖業の発展は世界的にも大きく期待されています。しかしながら昨今,安全な養魚飼料原料の安定的供給に関わる問題が顕在化し,水産養殖業の持続的発展に影を落とし始めています。本UJNR水産増養殖専門部会科学シンポジウムでは,日米両国の専門家間でそれらの問題に対する共通理解を促し,その解決のための道筋を模索します。 ・研究者交流 ・Guidance for UJNR Written Contributions(PDF:145KB) 作成 ・現地検討会 10月29日-11月1日 茨城県霞ヶ浦環境科学センター・水産工学研究所・ヒゲタ醤油(銚子市内)工場 |
||||||||||||||||||
| 38 | 2009年 (H21) 10月26日-30日 |
Texas A & M Universities' Harte Research Institute (Corpus Christi, Texas) | 飯田貴次 Rovert Iwamoto |
・シンポジウム「増養殖に係る水産業と水産コミュニティーの相互作用」 ・趣旨:沿岸環境管理,漁村,資源分配,経営コスト等において水産業と増養殖が果たす役割の相互作用と,それらに与える先端的技術の効果について焦点を当て議論する。米国側は沿岸域にどのような水産コミュニティーを作っていくか,日本側は地域産業の振興を意識した地域での取り組みに,それぞれ関心があることを念頭に,「地域おこし」を核にした話題提供を組織したい。 ・研究者交流 ・現地検討会 10月28日-10月30日 フラワーブラフの海産魚類ふ化場, テキサスA&M大学及びテキサス大学のエビ類・魚類の増養殖研究関連施設,オーツエルのエビ養殖場,テキサス州立水族館および実習船カルマ号によるエビ漁業の実習に関する視察 |
||||||||||||||||||
| 第8次3ヶ年計画 | ||||||||||||||||||||||
| 39 | 2010年 (H22) 10月24日-30日 |
鹿児島 | 飯田貴次 Micheal Rust |
・シンポジウム「養殖産業の現状と将来」 ・趣旨:養殖業の持続的発展を意識した開発研究の現状や最新の話題を提供しあうとともに,養魚産業の未来を考える総合討論を行う。 ・研究者交流 ・現地検討会 10月27日-30日 鹿児島大学水産学部,有村屋(水産加工),鹿児島県水産技術開発センター,垂水市漁協,鹿児島鰻(株),志布志栽培漁業センター,黒瀬水産(株)(ブリ養殖) |
||||||||||||||||||
| 40 | 2012年 (H24) 10月21日-26日 |
tde University of Hawaii East West Center (Honolulu, Hawaii) |
花房克磨 Michael Rust |
・シンポジウム「種苗生産技術」 ・趣旨:第39回の科学シンポジウムで明確となった種苗生産の課題に基づき,産卵や仔稚魚期(種苗期)の飼育に関連する科学的,技術的課題に着目する。 ・研究者交流 ・現地検討会 10月24日-26日 Oceanic Institute, Offshore Fish Farm, Kaloko Honokahau Hawaiian Fishpond, Natural Energy Laboratory of Hawaii Autdority |
||||||||||||||||||
| 41 | 2013年 (H25) 10月9日-13日 (シンポジウム) 12月10日-13日 (事務会議) |
札幌・函館(シンポジウム) 横浜・宮古(事務会議) |
花房克磨 Michael Rust |
・シンポジウム「最新の養殖関連技術」 ・第39回のシンポジウムで鍵となった課題,健全性や成長,食品としての養殖生産物の価値に関連したもので,養殖業を支援し,振興する先端科学技術に焦点を当てる。 ・研究者交流 ・現地検討会(10月11日-12日) 北水研千歳事業所,道立総合研究機構栽培水産試験場,北海道栽培漁業振興公社,北海道大学臼尻水産実験所 |
||||||||||||||||||
| 第9次3ヶ年計画 | ||||||||||||||||||||||
| 42 | 2014年 (H26) 9月29日-10月3日 |
Soutdwest Fisheries Science Center (SWFSC) (La Jolla, California) | 伊藤文成 Michael Rust |
・シンポジウム「養殖業に求められる育種研究の現状」 ・第41回の科学シンポジウムで明確となった第9次3カ年計画のテーマである「養殖業における育種研究」の1年目として,日米両国の育種研究の現状について焦点をあてた。 ・研究者交流 ・現地検討会 (9月30日-10月3日) Hubbs Sea World Research Institute (HSWRI), Soutdwest Fisheries Science Center (SWFSC), Scripps Institution of Oceanography(SIO), HSWRI white seabass hatchery, Long Beach Aquarium |
||||||||||||||||||
| 43 | 2015年 (H27) 11月10日-13日 |
水産総合研究センター西海区水産研究所,長崎大学,長崎県,佐賀県,大分県 | 伊藤文成 Michael Rust |
・シンポジウム「育種品種が産業および生態系に与える影響とその評価について」 ・第9次3カ年計画「養殖業における育種研究」の2年目。 ・研究者交流 ・現地検討会 (11月10日,12日-13日) 西海区水産研究所,長崎県総合水産試験場,小長井町漁業協同組合,佐賀県有明海水産振興センター,日本水産株式会社大分海洋研究センター,増養殖研究所上浦庁舎 |
||||||||||||||||||
| 44 | 2016年 (H28) 11月1日-4日 |
NOAA北西水産科学センター 米国ワシントン州シアトル市 |
伊藤文成 Michael Rust |
・シンポジウム「養殖における遺伝学と育種」 ・第9次3カ年計画「養殖業における育種研究」の最終年。 ・第10次三カ年計画の策定 ・研究者交流 ・現地検討会 (11月3日-4日) 二枚貝類養殖場,NOAAマンチェスター研究所,NOAA北西水産科学センター,魚市場 |
||||||||||||||||||
| 第10次3ヶ年計画 | ||||||||||||||||||||||
| 45 | 2017年 (H29) 10月16日-19日 |
広島国際会議場 広島県 |
伊藤文成 Michael Rust |
・シンポジウム「環境変化の影響を軽減する養殖の可能性」 ・第10次3カ年計画「環境変化における海面養殖」の1年目。 ・日米の共同研究の発展について意見交換 ・研究者交流 ・現地検討会 (10月18日-19日) 瀬戸内海区水産研究所,浜毛保漁業協同組合アサリ養殖場,マガキ・クルマエビ複合養殖場,広島県立総合技術研究所水産海洋技術センター |
||||||||||||||||||
| 46 | 2018年 (H30) 11月12日-16日 |
米国コネチカット州ミスティック市 | 伊藤文成 Michael Rust |
・シンポジウム「持続可能な食料供給と環境変化による影響低減のための養殖技術の応用」 ・第10次3カ年計画「環境変化における海面養殖」の2年目。 ・研究者交流 ・現地検討会 (11月12日-13日, 16日) コネチカット大学海藻研究室,カキ養殖場,アメリカ海洋大気庁(NOAA)ミルフォード研究所,海洋科学マグネット高校,スズキ閉鎖循環養殖場,ウナギ閉鎖循環養殖場 |
||||||||||||||||||
| 47 | 2019年 (R1) 11月12日-15日 |
沖縄産業支援センター 沖縄県 |
青野英明 Michael Rust |
・シンポジウム「環境変動による養殖生産への影響とその緩和に向けた研究」 ・第10次3カ年計画「環境変化における海面養殖」の最終年 ・第11次三カ年計画の策定 ・研究者交流 ・現地検討会 (11月14日-15日) 沖縄県栽培漁業センター,マグロ養殖場,琉球大学瀬底実験所,沖縄科学技術大学院大学(OIST),サンゴ養殖施設 |
||||||||||||||||||
| 第11次3ヶ年計画 | ||||||||||||||||||||||
| 48 | 2020年 (R2) 10月6日-7日 |
オンライン会議 | 青野英明 Michael Rust |
・新型コロナウイルス感染拡大によりシンポジウムを一年延期 ・オンラインで開催 ・ビジネスミーティングを実施 ・第11次三カ年計画「養殖業の疾病管理」の準備として魚病に関する意見交換を実施 |
||||||||||||||||||
| 49 | 2021年 (R3) 11月2日-4日 |
オンライン会議 | 青野英明 Michael Rust |
・新型コロナウイルス感染拡大により米国での開催に代えてオンラインで開催 ・ビジネスミーティングを実施 ・科学シンポジウムを実施 ・第11次三カ年計画「養殖業の疾病管理」の1年目 |
||||||||||||||||||
| 50 | 2022年 (R4) 11月14 日-16日 |
オンライン会議 | 青野英明 Janet Whaley |
・新型コロナウイルス感染拡大により日本での開催に代えてオンラインで開催 ・3年連続のオンライン開催。時差のため日本の朝,米国東海岸の夜にあたる2時間で3日にわたり開催 ・ビジネスミーティングを実施(11/14),50回記念事業と功労者表彰 ・第11次三カ年計画「養殖業の疾病管理」の2年目 ・科学シンポジウムを実施,米国6題,日本7題(11/15-16) |
||||||||||||||||||
| 51 | 2023年 (R5) 8月29日-9月1日 |
Freeport, Maine | 青野英明 Janet Whaley |
・ビジネスミーティングを実施(8/29)フリーポート。プロシーディングス出版,第12次三カ年計画の決定。 ・第11次三カ年計画「養殖業の疾病管理」の3年目 ・科学シンポジウムを実施(8/29-30),米国12題,日本6題 ・現地検討会(8/31-9/1):民間検査会社,メイン大ダーリン海洋センター,カキ養殖場,米農務省国立冷水海洋養殖センター,水産養殖共同研究センター,メイン大学共同普及診断研究所 |
||||||||||||||||||
| 第12次3ヶ年計画 | ||||||||||||||||||||||
| 52 | 2024年 (R6) 11月5日-8日 |
三重県伊勢志摩 シンフォニアテクノロジー響ホール伊勢 |
三木奈都子 Janet Whaley |
・ビジネスミーティングを実施(11/5) ・第12次三カ年計画「持続可能な水産養殖の新時代-次の50年間の研究,教育,コラボレーション」の1年目 ・「持続可能で強靱な水産養殖のための次のステップ-代替飼料,育種,健康管理,藻類養殖,生態系管理」をテーマに科学シンポジウムを開催(11/5-6) ・米国7題,日本14題の研究発表 ・現地検討会(11/7-8):三重県水産研究所,水産研究・教育機構南勢庁舎,カキ養殖場,三重大学水産実験所,真珠博物館 |
||||||||||||||||||
- リンク一覧